このページでは「力のはたらき」について中学生向けに解説していきます。
「力のはたらき」はこのページを読めばバッチリです!
中学理科の成績を伸ばせる塾!「さわにい理科塾」を始めました!詳しく知りたい方はこちら。さわにい本人のサポートで成績UPです!
 ねこ吉
ねこ吉ねこ吉です。みんなよろしく!
では、力のはたらきの学習スタート!
力のはたらき
力がはたらいたときの現象
まずは「力のはたらき」
つまり物体(物)に力が加わると、どのようなことがおこるか
を学習していくよ。
さっそくだけど、
物体に力が加わると、どのようなことがおこるかな?



力って何でしょうか…?
難しく考えないでいいよ。「物体に力が加わる」というのは
- 物体を押したり
- 引っ張ったり
- たたいたり
- けったり
- 投げたり…
物体にこれらのことをすると、ものはどうなる?ということだね。
言えるだけ言ってみよう!
物の種類は、固いものでも、柔らかいものでも、どんなものを想像してもいいよ!



そんなの、たくさんあるよ!物体に力を加えると、「つぶれる・こわれる・伸びる・曲がる・飛ぶ・落ちる・折れる・破れる・動く・へこむ・進む・止まる・開く・閉まる・ちぎれる・支える・ゆれる。」あと。ええと…。
いいね!ねこ吉君!
全部大正解だよ。
だけど、探せばまだまだあるよね?
それに、全部はとても覚えきれない。
こういうときに理科では、
似たものをまとめて整理していくんだよ。
では、ねこ吉が言った力のはたらきの中から、
似ているものを色分けしてみるよ。
つぶれる・こわれる・伸びる・曲がる・飛ぶ・落ちる・折れる・破れる・動く・へこむ・進む・止まる・開く・閉まる・ちぎれる・支える・ゆれる。
こんな感じかな?
さらに色ごとに並べかえてみるね。
① つぶれる・こわれる・伸びる・曲がる・折れる・破れる・へこむ・ちぎれる
② 飛ぶ・落ちる・動く・進む・止まる・開く・閉まる
③ 支える
このようになるよ。
まずは①を見てみるよ。
「つぶれる・こわれる・伸びる・曲がる・折れる・破れる・へこむ・ちぎれる」
だね。
これらを整理して一言で表すことはできるかな?



わかった!どれも物体の形が変わっているんだ!
その通り!
つまり、
「力のはたらき(物体に力が加わると、どのようなことがおこるか)」
の一つ目は、物体の形が変わる。ということなんだね。
力のはたらき①
物体の形が変わる。(物体が変形する)
次に②を見てみるよ。
「 飛ぶ・落ちる・動く・進む・止まる・開く・閉まる」だね。
これらは物体を動かしたり、動いているものを止めたり、動く方向を変えたり。
ということだね。
つまり
「力のはたらき(物体に力が加わると、どのようなことがおこるか)」
の2つ目は、物体の動きが変わる。ということなんだ。
力のはたらき②
物体の動きが変わる。
最後に③だね。
「③ 支える」。これはそのままだね。(笑)
ただ、覚えるのは簡単だけど、少しわかりにくいから注意してね。
例えば手のひらの上に物体を置いて、動かさない場合。
これは手は物体に力を加えているかな?
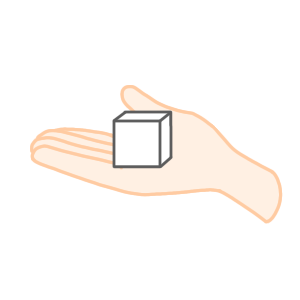
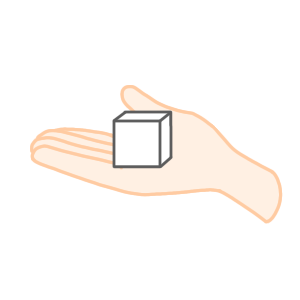
ねこ吉はどう思う?



うーん。物体は動いてないし、力は加えていないのかな?
そんな気もしてしまうよね。
だけど、上に書いているように、これも支えているから、
手は物体に力を加えているんだ。
しっかりと理解してね。
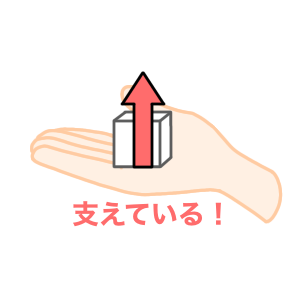
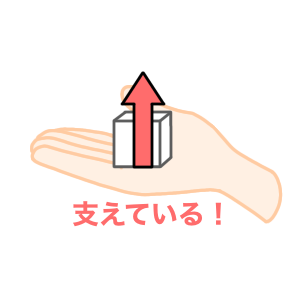
もしも、この手が無かったら、物体はどうなると思う?
あたりまえだけど、重力で下に落ちるよね?
このように、落ちないように支えるというのも、力のはたらきの1つだと、しっかりと覚えよう!
力のはたらき③
物体を支える。
まとめ
まとめるよ。力のはたらき(物体に力が加わると、どのようなことがおこるか)は次の3つ。
- 物体の形が変わる。(物体が変形する)
- 物体の動きが変わる。
- 物体を支える。
だよ。しっかりと覚えておこう。
みんなお疲れ様。
次のページでは「いろいろな力」という中学で学習する力の種類を解説しています。
おまけ
「力のはたらき③」について
おまけは少し難しい話だから、理科が苦手な人はとばしていいよ!
力のはたらき3つを学習したけど、
「力のはたらき③ 物体を支える」は、本によっては
「力のはたらき③ 物体をもちあげる、また支える」というふうになっている場合があるんだ。
この「物体をもちあげる」は
「力のはたらき② 物体の動きを変える」
のなかまの気がするね。
だけど、この場合のもちあげるは、「ずっと真上に、同じスピードでもちあげ続ける」という意味なんだ。
これなら、力は加えているけど、物体の動きは「変化は」していないね。
同じ向きに同じスピードでうごいているからね。
だから、「物体をもちあげる」は「力のはたらき③ 物体を支える」のなかまになっているんだよ。
力のはたらきの「はたらき」はひらがなでよい
「力のはたらき」と書く時の「はたらき」はひらがなでいいよ。
教科書もひらがなだよね?
これはきっと「働き」と書くと、
「人間が仕事をしてお金をかせぐ。」
というイメージになるから、ひらがなにしているんだね!
以上でおまけを終わるね。 お疲れ様☆
力のはたらきの学習はこれで終わり!
続けて力の学習をしたい人は、下のボタンを使ってね!
さわにいは、登録者8万人の教育YouTuberです。
中学の成績を上げたい人は、ぜひYouTubeも見てみてね!
また、2022年10月に学習参考書も出版しました。よろしくお願いします。
他のページも見たい人はトップページへどうぞ。


今なら相談無料です

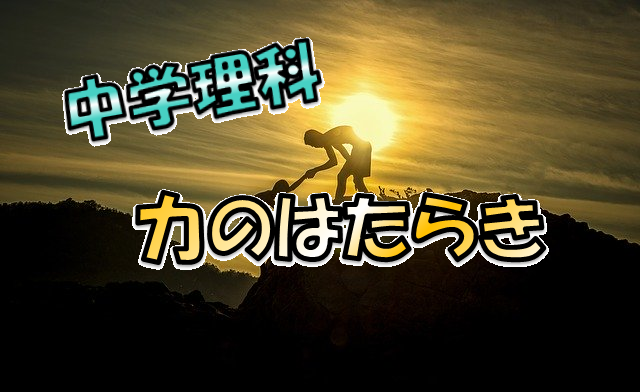


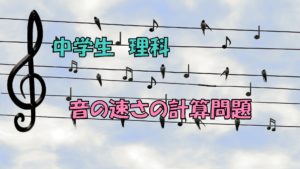


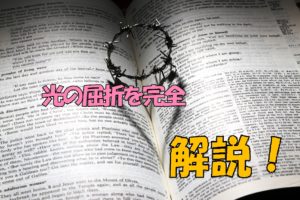
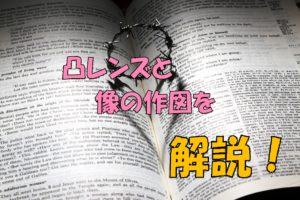
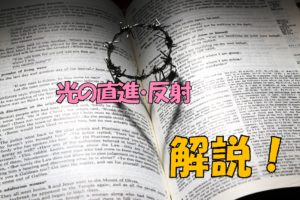


コメント