このページでは
- 力の矢印
- 矢印の書き方
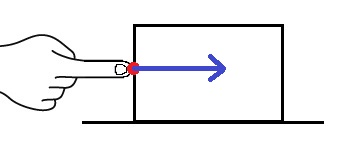
を中学生向けに説明していきます。
中学理科の成績を伸ばせる塾!「さわにい理科塾」を始めました!詳しく知りたい方はこちら。さわにい本人のサポートで成績UPです!
 ねこ吉
ねこ吉ねこ吉です。みんなよろしく!
では、力の矢印の学習スタート☆
(▼時間がある人は動画でも学習できるよ!)
力の矢印で力を表す
力の矢印の学習を始めよう!



力の矢印って何ですか?
「力」は目で見ることができないんだ。
例えば指で物体を押してみよう。
こんな感じ。→ 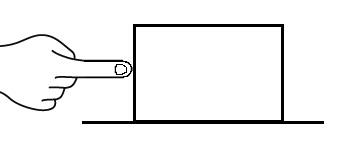
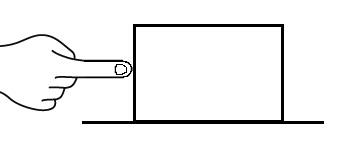
このとき、物体を押す「力」は目で見えないよね?
だけど、力の矢印を使って表すと、
「力」がイメージしやすくなるんだよ。
こんな感じ。→ 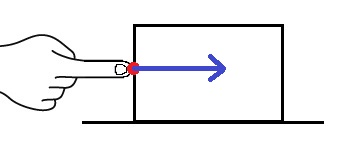
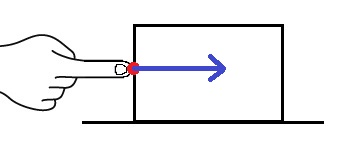



ほほう。なるほど!
さらに力の矢印の便利なところは
- 力を加える点(作用点)
- 力を加える向き
- 力の大きさ
の3つが簡単にわかる。ところにあるんだ!
1つずつ確認していこう!
まず、「①力を加える点(作用点)」は
下の図1の赤色の点だよ。ここに力を加えているんだね。
図1 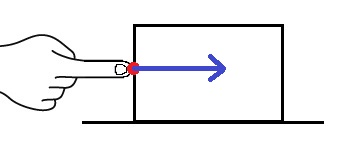
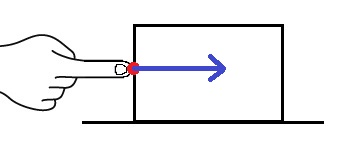
そして、図の矢印の向きが「②力を加える向き」になるよ。
この場合は右側に押しているということだね。
最後に「③力の大きさ」は矢印の長さになるんだ。
例えば上の図1と下の図2では矢印の長い図2のほうが大きな力を加えているということだね!
図2 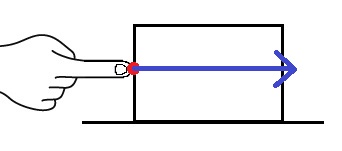
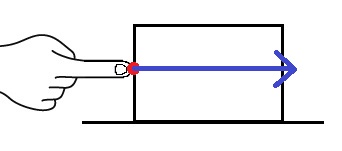
これらが力の矢印の基本だよ。



目に見えない「力」がイメージしやすくなるね!
注意を2つ言っておくね。
注意① 面での作用点の書き方。
図3 手のひらで押す
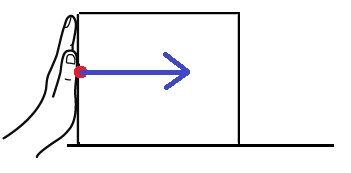
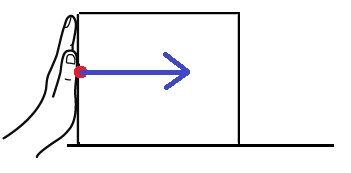
図4 物体が床を押す
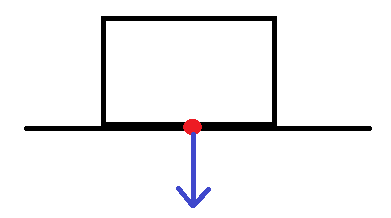
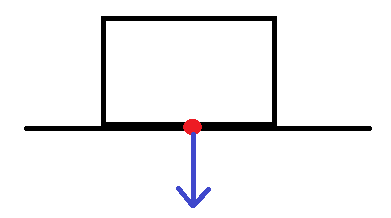
図3、図4のように、点ではなく、広い部分で押す場合は、
面の中心あたりに作用点を書けばいいよ!
注意② 力の矢印の長さ
力の大きさは、矢印の長さで表すことができるんだよね。
テストでは、1Nの力を1cmの長さで書け。
とか、1Nの力を1マスで書け。のようになることがほとんどだよ。
最後に例題で確認してみよう。
例題 物体を3Nの力で押した。1Nの力を1マスとして、この力を矢印で表せ。
答え 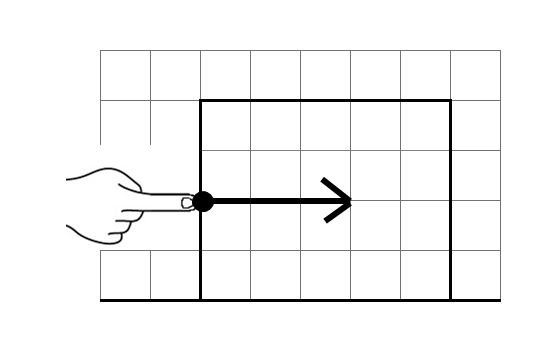
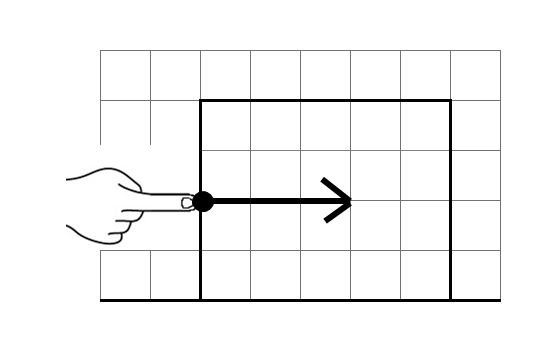



1Nで1マスなら、3Nの力は3マスで書けばいいんだね!
力の矢印の書き方
ここからは力の矢印の書き方のきまりを学習するよ。とても大切なところだから、丁寧に読んでね。
力の矢印の書き方には、
とても大切なポイントがあるんだ。
力の矢印の書き方の重要ポイント!
問題を読んで
- 「重力」という力の矢印を書くのか
- 「重力以外」(押す力、引く力、支える力など)の力の矢印を書くのか
を確認する!
ことなんだ。
この①と②をごちゃ混ぜにすると、力の矢印の書き方がわからなくなるよ。
問題文をしっかりと読めば、
- 「重力の矢印」を書くのか
- 「重力以外の矢印」を書くのか
簡単にわかるから、必ず確認するんだよ。
それでは、①重力の矢印の書き方から学習していこう!
「重力」の矢印の書き方
重力の矢印の書き方は簡単だよ。
書き方①
重力を書きたい物体の中心に作用点を書く。
書き方②
質量(g)を力(N)になおす。
書き方③
力の大きさの分、下方向に矢印を書く。
これでOK。例題をやりながら確認しよう!
例題の力の矢印を、1Nの力を1cmの長さとして書け。
例題① 100gのおもりにはたらく重力を書け。


質量100gのおもりが天井から吊るさっているんだね。
まずは、
書き方①
重力を書きたい物体の中心に作用点を書く
だよ。作用点を「重力を書きたい物体の中心」
に書こう!(だいたい真ん中ならOK!)
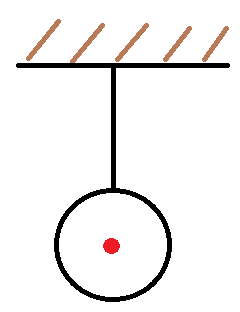
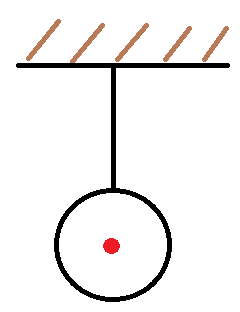
こんな感じだね!
次に書き方②
質量(g)を力(N)になおす。
だね。質量100gを力(重力)になおすと、1Nだったよね!
そして、この問題では
「1Nの力を1cmの長さとして書け。」
となっているから、1cmの矢印を書けばいいんだ。
最後は書き方③
力の大きさの分、下方向に矢印を書く。
だね。「重力」は絶対に下方向にしかはたらかないよ。
下向きに1cm分矢印を書けばいいね。
答え → 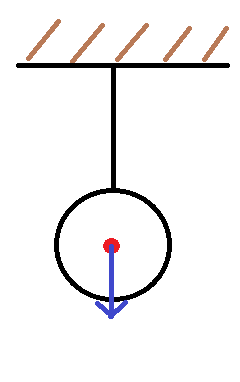
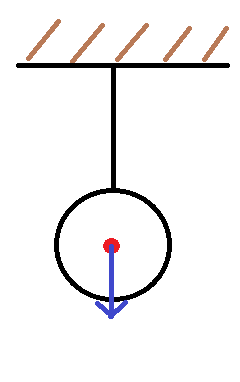
こんな感じだね。
テストではしっかりと矢印の長さを測ったり、マス目があればそれに合わせて書くんだよ!



中心に作用点を打つ。質量を力になおす。下向きに矢印を書く。でいいんだね!
そうだね。矢印の長さに気を付けてね。
それでは例題②にいこう!
例題② 200gの物体にはたらく重力を書け。


質量200gの物体が置いてあるんだね。
まずは、書き方①
重力を書きたい物体の中心に作用点を書く。
だよ。作用点を「重力を書きたい物体の中心」に書こう!
ここで、絶対に点を書く位置で悩んではいけないよ!
「重力を書け」という問題だから、
自信をもって中心に作用点を書いてね!


こんな感じ!
次に書き方②
質量(g)を力(N)になおす。
だね。質量200gを力(重力)になおすと、2Nだね!
そして、この問題では「1Nの力を1cmの長さとして書け。」となっているから、2cmの矢印を書けばいいんだ。
最後に書き方③
力の大きさの分、下方向に矢印を書く。
だね。「重力」は絶対に下方向にしかはたらかないよ。
だから、下向きに2cm分矢印を書けばいいね。
答え → 

これでいいね!
基本はこれでOK。あとは練習量が大切なんだ!練習問題を4つ出すから、考えてみてね!
悩むうちはまだ練習が足りないよ☆
問1~4の力の矢印を、1Nの力を1cmの長さとして書け。
問1 100gの物体Aにはたらく重力


問2 150gの物体Bにはたらく重力


問3 100gの物体Cにはたらく重力


問4 80gの物体Dにはたらく重力


問1の答え 問2の答え




問3の答え 問4の答え




正解することができたかな?(みんなは矢印の長さをしっかり測ろうね。)
ポイントは作用点を打つ位置だよ。
- 「Aにはたらく重力」なら「Aの中心」
- 「Cにはたらく重力」なら「Cの中心」
というように簡単に考えればいいんだよ。
物体が重なっていても、吊るさっていても関係ないんだ。
図を見て迷ったらだめだよ!
これで 「① 重力の矢印の書き方」の説明を終わるよ。
- 重力を書きたい物体の中心に作用点を書く。
- 質量(g)を力(N)になおす。
- 力の大きさの分、下方向に矢印を書く。
書き方のポイントをしっかりと覚えておこう!
「重力以外」の矢印の書き方
さて、ここからは「重力以外」の力の矢印の書き方だよ!
まず一番大切なことは、「重力」とは書き方が別だから、
「重力の書き方」と、今から説明する「重力以外の書き方」を混ぜないこと!
だよ!



わかりました☆
ところで先生、「重力以外」の力にはどのようなものがあるの?
簡単だよ。
- 「〇〇を押す力」
- 「△△を引く力」
- 「□□を支える力」とか。
とにかく「重力以外」だったら今からの書き方をするようにしてね!
それでは説明を始めるよ!
書き方①
力を加えるものと、加えられるものが接触している点に作用点を打つ。
書き方②
力(N)の大きさを確認する。
書き方③
力の大きさの分、向きを自分で考えて矢印を書く。
この書き方で全てOKだよ。



確かに重力の書き方と違うね。混ぜないようにしないと!!
うん。気を付けてね。
1番の違いは作用点を打つ位置だよ。
重力の場合は、書きたい物体の中心でよかったけれど
重力以外の場合は、接触(せっしょく)している点なんだよ!



接触しているところって?
触っているところということだね。
大丈夫。簡単だよ。例題を解きながら確認していこう。
例題の力の矢印を、1Nの力を1cmの長さとして書け。
例題① 指で物体を押す2Nの力の矢印を書け。
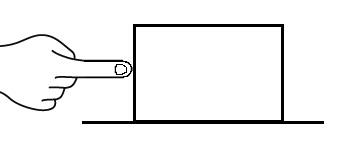
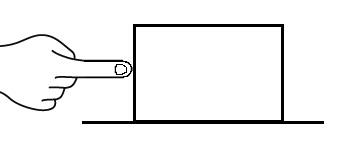
書き方①
力を加えるものと、加えられるものが接触している点に作用点を打つ。
からだね。
ここで、力を加えるのは「指」、力を加えられるものは「物体」だね。だから



指と物体が接触しているところに点を打てばいいのか!
うん!このようになるね!→ 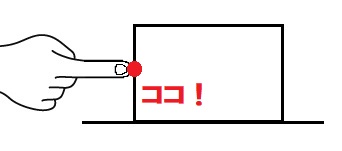
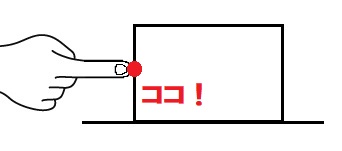
書き方②にいくよ。
書き方②
力(N)の大きさを確認する。
だね。問題文に2Nと書いてあるから力の大きさは2だね。
重力と違って質量からなおさないでいいから楽だね☆
最後に書き方③だね。
書き方③
力の大きさの分、向きを自分で考えて矢印を書く。
矢印の向きは、「重力以外の力」を書く場合は自分で向きを考えなければならないんだ。
さて、「指で物体を押す」の力の向きはどの向きかな?
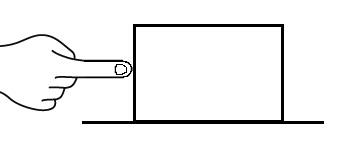
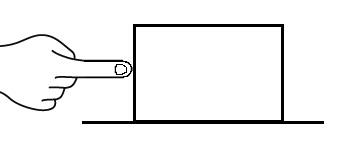
この図から「押す」といえば、右向きだね。
そして、2Nの力だから、2cmで書けば答えは下のようになるよ。
答え → 

なれれば簡単だよ。
例題② 指がひもを引く3Nの力の矢印を書け。
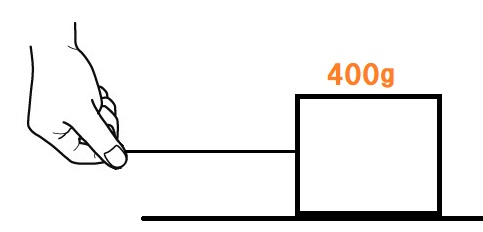
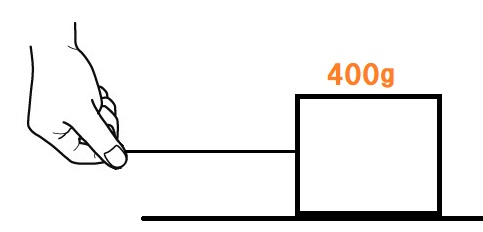
書き方①
力を加えるものと、加えられるものが接触している点に作用点を打つ。
からだね。
ここで、力を加えるのは「指」、
力を加えられるものは「ひも」だね。
だから「指」と「ひも」が接触しているところに点を打つんだね。
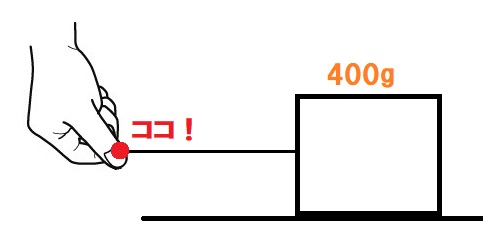
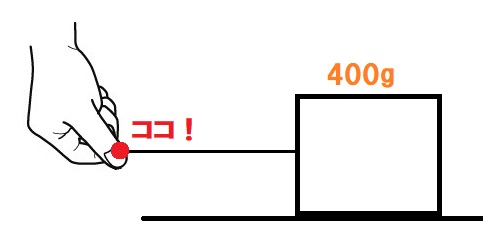
書き方②にいくよ。
書き方②
力(N)の大きさを確認する。
だね。問題文に3Nと書いてあるから力の大きさは3だね。
質量からなおさないでいいんだね。
ちなみに、問題文の400gはひっかけで、この例題ではまったくつかわないよ。
ひっかからないでね。(もちろん物体の重力を書け。という問題だったら使うけどね。)
最後に書き方③だね。
書き方③
力の大きさの分、向きを自分で考えて矢印を書く。
矢印の向きは、「重力以外の力」を書く場合は自分で向きを考えなければならないんだよね。
さて、「指でひもを引く」の力の向きはどの向きかな?
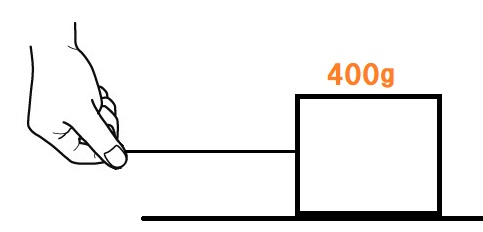
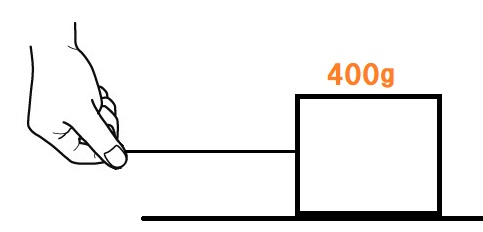
この図から「引く」といえば、左向きだね。
そして、3Nの力だから、3cmで書けば答えは下のようになるよ。
答え → 

テストではみんなは長さを測るんだよ!
基本はこれでOK。あとは練習量が大切だよ!
難しい練習問題を出すから、考えてみてね!
考え方の基本はこれまで通りだよ☆



作用点の打つ場所に注意だね。接触しているところというのは「○○が△△を~」の○○と△△の間ということだね。
問1~4の力の矢印を、1Nの力を1cmの長さとして書け。
問1 指がひもを引く2Nの力
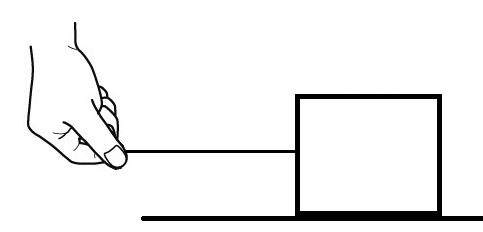
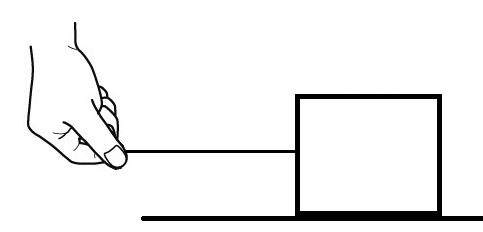
問2 ひもが物体を引く2Nの力
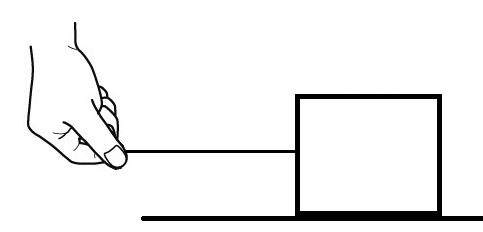
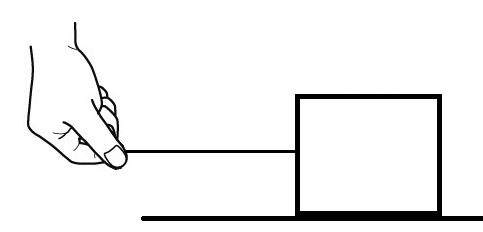
問3 物体が床を押す1Nの力
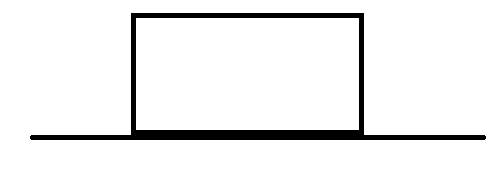
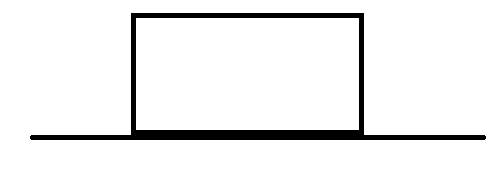
問4 床が物体を支える2Nの力
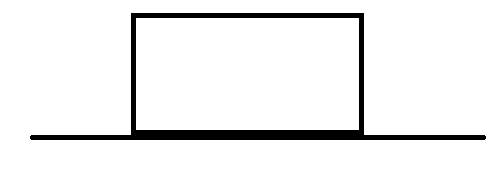
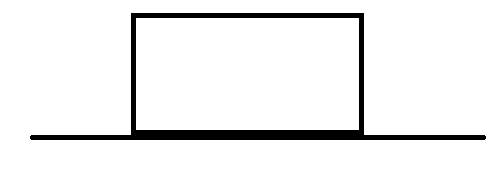
問5 AがBを押す1Nの力


問6 Bが床を押す3Nの力


問7 おもりがひもを引く2Nの力
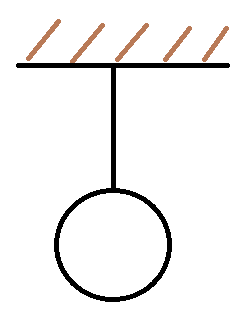
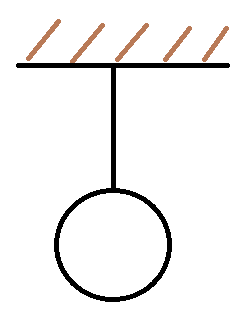
問8 ひもが天井を引く2Nの力
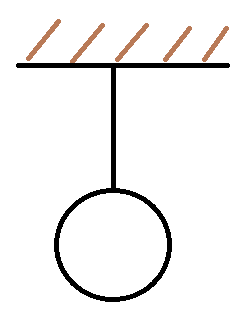
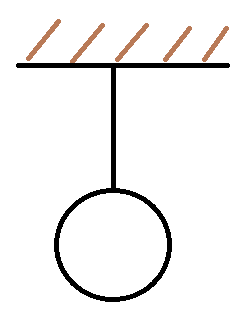
問1の答え 問2の答え
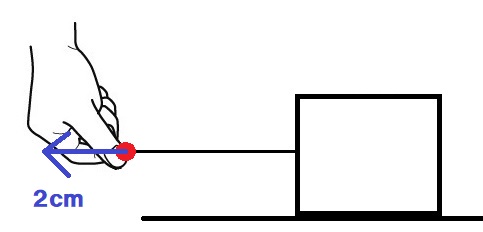
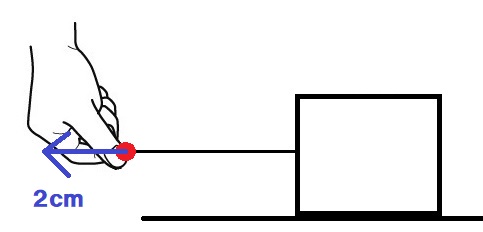


問3の答え 問4の答え




問5の答え 問6の答え




問7の答え 問8の答え




どうかな?何回も確認してね。
(みんなは矢印の長さも測るんだよ。)
ポイントは作用点を打つ位置だよ。
加えている力と加えられている力が接触しているところ
接触しているところというのは「○○が△△を~」の○○と△△の間
というのを確認しながら、何度も問を確認してみようね。
これで「② 重力以外の力の書き方」の説明を終わるよ。
書き方①
力を加えるものと、加えられるものが接触している点に作用点を打つ。
書き方②
力(N)の大きさを確認する。
書き方③
力の大きさの分、向きを自分で考えて矢印を書く。
この順番を覚えておこうね!
これで力の矢印の書き方の学習はおしまいだよ。
「重力」も「重力以外の力」もどちらも書けるようになろうね!
この知識は高校生になっても役立つよ!長かったけれど、みんなよく頑張ったね☆
お疲れ様!自分をほめてあげよう!
…ほめたかな?笑
続けて力の学習をしたい人は、下のボタンを使ってね!
①力のはたらき
②いろいろな力の種類
③力の単位、力と質量の関係
④フックの法則
⑤力の矢印の書き方←今ここ
⑥質量と重さの違い
⑦圧力とは何か、圧力の計算
⑧水圧
⑨浮力
⑩気圧
さわにいは、登録者8万人の教育YouTuberです。
中学の成績を上げたい人は、ぜひYouTubeも見てみてね!
また、2022年10月に学習参考書も出版しました。よろしくお願いします。
他のページも見たい人はトップページへどうぞ。


今なら相談無料です



またねー!

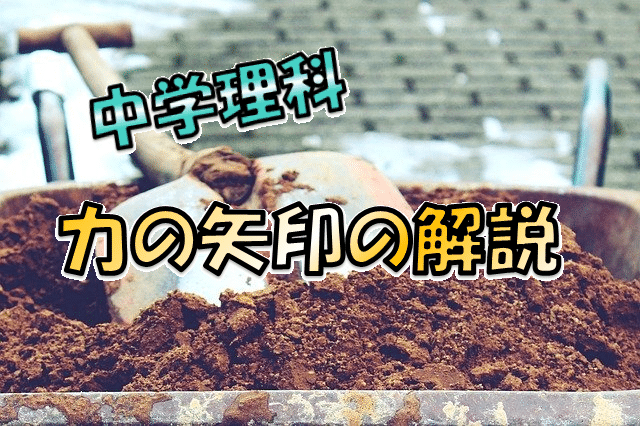


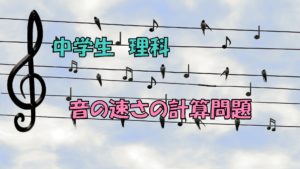


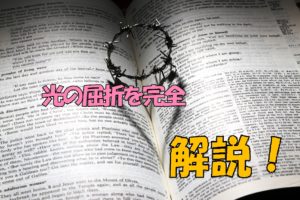
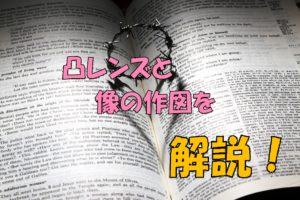
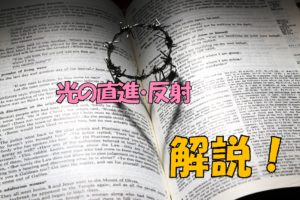


コメント